私があの子と出会ったのは、あの子が三歳の誕生日のときだった。
私があの子と出会ったのは、あの子が三歳の誕生日のときだった。
あの子は私を一目見たときから気に入り、以来、いつ何をするにしてもずっと一緒に過ごしていた。
晴れた日には近くの公園であの子とあの子のお友達と一緒にままごとをしたり、雨の日にはお部屋の中で一緒に絵本を読んだりしていた。
まだ小さいあの子は加減というものを知らず、時には私を振り回して腕をもいでしまったり、泥団子を無理やり私に食べさせようとして、私を泥だらけにしたりして、その度にあの子のお母さんに泣きついて、私を綺麗に繕ってもらっていたのは、今ではいい思い出だ。
私は、ずっとずっとあの子のお気に入りだった。
度重なる修繕と洗濯とで、次第に色あせ、ボロボロになっていった私だけれど、それでもあの子は私を大事そうに抱え、一緒に遊んでくれていた。
人形である私に、これに勝る幸せはなかった。
あの子が朝目を覚ますと、私に微笑んで「おはよう」と言い、私を大事に抱えながら一緒に食事をして(といっても人形の私には食べることはできないのだが)、日が暮れるまであの子と一緒に遊びまわり、最後にはベッドで一緒に眠る。



ああ……
どうか……
どうかいつまでも……
こんな日々が続きますように……


当時の私は、あの子の部屋の窓から差し込む月の光に、そう何度もお願いした。
当時の私は、あの子の部屋の窓から差し込む月の光に、そう何度もお願いした。
けれどもそんな願いが叶うはずはなかった。
人形である私と違って、人間とは成長していくもの。
そしてそれは、私が大好きなあの子も例外ではない。
あの子が小学校を卒業し、中学に入ったころからだろう、私と遊ぶということをしなくなってしまった。
部活で毎日日が暮れるまで汗を流して勉強や宿題をし、密かに憧れる先輩に胸を焦がすことに青春を費やしているのだから、それも仕方がないのかもしれない。
正直に言えば、寂しかった。
あれほど毎日のように一緒に遊んでいたあの子が、ある日を境にぱったりと私と遊ぶということをしなくなったのだ。
あの子がまだ小さいころから一緒にいた私からすれば、それは凄く寂しいことだった。
けれども仕方がない。人間とはそういうものであり、あの子もまたその人間の一人なのだから。



仕方が無い……
そう……
仕方が無いことなんだ……


そう諦め、寂しさを覚えながらも、けれど私はまだ幸せを感じていた。
なぜなら、あの子は私で遊ぶことはしなくなったけど、決して私を捨てるようなことはしなかったから。
色褪せ、腕や足が千切れる度に繕ってもらって、かなりボロボロになってしまった私を、それでも大事そうに窓際に飾ってくれていたのだから。
年末に大掃除で部屋を片付けるときも、使わなくなった小物やら筆記用具やらが姿を消していく中で、決して私だけは捨てようとしなかった。
それがとても嬉しかった。
もう私で遊んでくれることはなくなってしまったし、幼いころのように私に話しかけてくれることもなくなってしまったけれど、それでも本当に大切にしてくれているのが、私は凄くうれしくて、幸せだった。
そして何よりも……。
あの子の幸せな姿を見ることが嬉しかった。
中学で始めた部活でレギュラーとして選ばれたと嬉しそうに友達や両親に報告する姿も、好きな人ができたと友達に電話をする姿も、中学を卒業して真新しい高校の制服に身を包んで、これから始まる新しい青春への期待に胸を膨らませる姿も、そして初めてできた彼氏を家に呼んで、初めてキスをして照れくさそうに微笑む姿も、そのどれもがあの子にとって幸せそうで……、私はそんなあの子を見ているだけで幸せだった。
逆に、テストで悪い点数を取ってしまって、親に怒られてしまったときや、部活で試合に負けてしまったとき、そして彼氏に振られてしまったときの悲しそうな姿を見ているときは、それでもただ見続けることしかできない人形の体に、もどかしさを感じていた。
そうして長いときが過ぎ、あの子はやがて高校を卒業して、遠くの大学に通うために一人暮らしを始めることになった。
そしてついにやってきた引っ越しの日。
あの子は自分が持っていく荷物を纏め終え、ふと窓際に飾られた色褪せた私にそっと手を伸ばし、そっと抱き上げてくれた。
私と一緒に遊ばなくなってから随分と長い時間、あの子に触れられることがなかった私は、久しぶりに感じたあの子の変わらぬ温もりに歓喜した。
抱き上げてもらったときの視線の高さと、布の肌に触れる柔らかさに、あの子の成長を感じ取れて、私は嬉しくなった。
そんな私をそっと胸に抱きしめて、私を置いていくことを謝った。



小さいころからずっと私といてくれたのに……
あなたを連れていけなくて……ごめんね……





何を謝る必要があるの?
何を泣く必要があるの?
これはいつかは来る必然の別れ
いつまでも一緒にいられないことは分かっていたこと
だから謝る必要はないよ
私はあなたに大事にされて嬉しかったのだから……
だから泣かないで?


声にならない声で慰める私を最後に愛おしそうに撫でて、あの子は去っていった。
それからどのくらいの年月が経ったのだろう。
私はあの子が去っていった日からそのままにしてある部屋で、今も変わらず、窓際にぽつんと飾られている。
来る日も来る日も、私はあの子のことを考えていた。



元気でやっているかな……?
風邪は引いてないかな……?
怪我はしていないかな……?
恋人はできたのかしら……?
一人で暮らしていて寂しく泣いていないかしら……?





会いたい……、一目でいいからあの子に会って、元気そうな姿を……幸せそうな姿を見てみたい……


そんな思いを募らせながら、日々を過ごしていたある日のことだった。



…………っ!?


突然、私は自分の中に不安が沸き起こるのを感じた。



人形の私にそんなことがあるはずがない……
きっと気のせいだ


そう思ってみても、私の中の不安は消えることはなく、むしろどんどん膨らんでいった。



もしかしてあの子に何かあったのかしら!?


そう思って、私はその沸き起こる不安の源泉に意識を集中してみた。
そして予感したもの。
それは、あの子に脅威が迫りつつあることだった。
それも、あの子の命に関わるような、大きくて凶悪な脅威。
今はまだだけど、その脅威は程なく彼女を襲うだろうことを予期した私は、一つの衝動に支配される。



助けなきゃ!


長い年月をかけて、私は月から降り注ぐ魔力を全身に浴び、蓄積してきたのだ。今の私にならそれができるはずだ。
そう思い、自らの体に満ちる魔力に思いを乗せて願う。



あの子を助けたい!


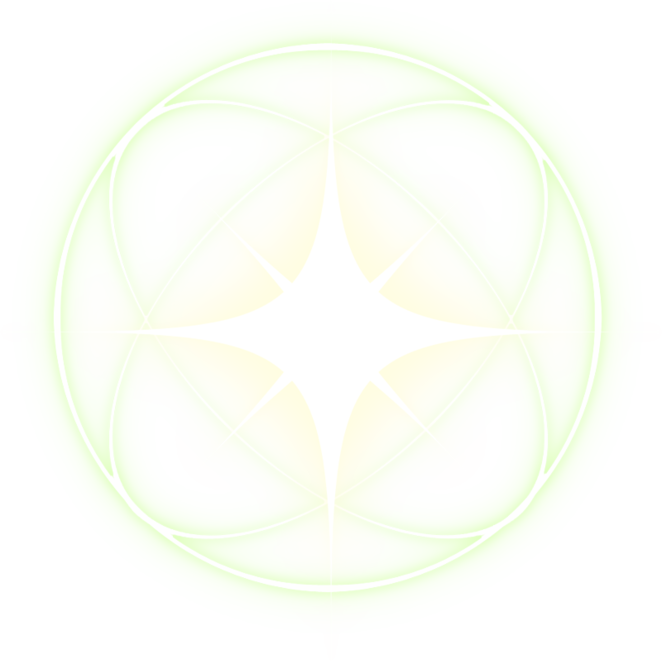
瞬間、私の中の魔力が願いを受け取り、私の体を怪異へと作り変えた。
けれど、私はそんなことを気にすることなく、行動を開始する。



まずはあの子の元へ行かなくちゃ……
でもいきなり行ったら驚くよね?
となると、まずは連絡しなきゃ……!


私は部屋を飛び出して電話帳を引っ張り出すと、あの子の携帯電話に電話をかける。
僅かな呼び出し音の後で、受話器からあの子の声が聞こえた。



もしもし……?
お母さん……?
どうかした?


ああ……。
あの子の声を聞くのは何年ぶりだろう……。
私の胸の中を、狂おしいほどの歓喜が暴れまわるけど、今はそんなことにかまけている暇はない。
私は頭を振って気を取り直すと、電話口のあの子に向かって話しかけた。



もしもし?
私、メリーさん……
今からあなたの元へ行くわ……





…………?


一瞬、電話の向こうからあの子の怪訝そうな空気が伝わってきたけれど、私はそれを懸命に無視して電話を切ると、記載された住所を頭に叩き込んで家を飛び出す。
ちなみにメリーさんとは、あの子が幼いころにつけてくれた私の名前だ。
それはともかくとして、体を懸命に動かして電車に飛び乗り、いくつか乗り継ぎをして、ようやくあの子が住む街に辿り着く。
都会特有の人通りの多さに内心で驚きながらも、電話機を見つけた私はすぐに飛びついて、あの子に電話をかけた。



……もしもし?


程なくして帰ってきたあの子の声は、知らない番号からの電話だったからか、困惑を含んでいた。
私は、それでもまだあの子が無事なことに安堵し、用件を手短に伝える。



もしもし?
私、メリーさん……
今、あなたが住む街についたわ……





…………え?


困惑する彼女の声を振り切って、私は電話を切ると、すぐさま駆け出した。
この街に着いたときから、彼女の気配を強く感じると同時に、彼女へと迫りつつある脅威の気配もまた強まりつつあったからだ。
そうして私は、時には走る車につかまり、時には自転車で駆ける若者に便乗して移動して、どうにかあの子が住むアパートのすぐ近くのコンビにまで辿り着き、再び電話機を発見する。
手早く番号を叩き込んで、彼女に連絡。



……あの……もしもし……?


どこか怯えを含む声に、私は精一杯の「大丈夫だよ」という気持ちを込めて口を開く。



もしもし?
私、メリーさん……
今、あなたの家の近くのコンビニにいるの……





……っ!?
ひっ……!?


短い悲鳴と共に、彼女のほうから電話を切る。



はて……?
私は何か怖がらせるようなことを言ったのかな?


そんな疑問を、慌てて頭を振って追い払った私は、すぐさま駆け出して、あの子が住むアパートの下に辿り着いた。
そして、途中で拾った誰かの携帯電話から電話をかける。



…………?





もしもし?
私、メリーさん……
今、あなたのお家の前にいるわ……


だから早く扉を開けて!
そんな私の願いもむなしく、彼女は恐怖に怯えたように電話を切ってしまう。



どうして……?


そんな疑問を頭に浮かべた私は、直後に誰かが階段を上って、ゆっくりとあの子の部屋へと近づきつつあるのを感じ取る。



……!?
時間がない!!


そう思った私は、急いであの子の部屋の僅かに空いた窓から体をねじりこんで中へと入る。



早く……!
一秒でも早く、あの子のところへ!


焦りでもつれる足を叱咤して懸命に走った私は、ついに懐かしいあの子の後姿を捉えた。
私が最後に見た時と変わらない長い髪だけど、体つきはより女性らしい丸みを帯びているように見える。
ちらりと覗いた左手の薬指には、きらりと光る指輪が収まっていて、あの子が今も幸せに暮らしているのだと分かった。
それだけで嬉しくて涙が滲んでしまうけど、今はそんな場合じゃないことを思いだして、急いで涙を拭う。
すでに脅威はあの子の部屋の中へと入ってきており、あと数秒もすればあの子の目の前に現れてしまう。
その前に、と私は直接あの子の背中に声をかけた。



こんばんは……
私、メリーさん……
今、あなたの後ろにいるの……


だから安心して……。
そんな思いをこめた言葉。



っ……!?


直後、びくりとあの子の肩が震えると同時に、ついに脅威――全身をロングコートで覆った一人の男があの子のすぐ後ろに辿り着いてしまった!
ゆっくりと振り返るあの子と、ぎらりと光るナイフが交差する。
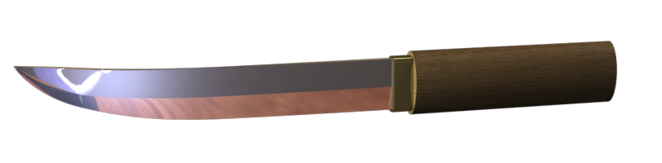



させない!!


その直前に、私は全身の力を振り絞って、ナイフとあの子の間に滑り込み、その身でナイフを受け止めた。



何だこの人形は……!?


男が驚き、慌ててナイフを引き抜こうとするけどもう遅い。
あの子を害するものを、私は許さないのだから。
ずぼっとナイフが引き抜かれると同時に、私は男からナイフを奪い取り、思いっきりその男の腹に突き刺してやった。
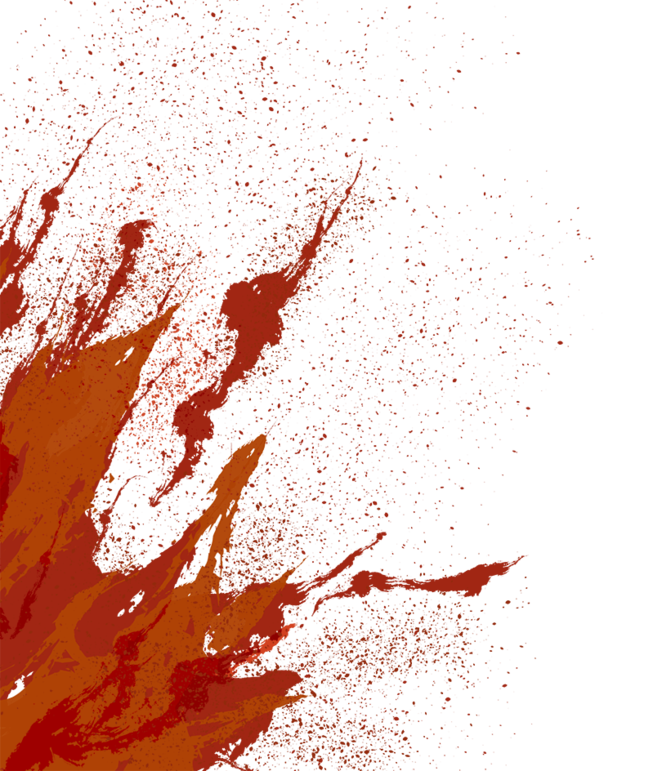



ぎゃぁぁああああああああっ!!


汚らしい悲鳴を上げながら、玄関から転がり出て行く男。
同時に床へと落下した私は、混乱するように私と男が去っていった方向を交互に見つめる彼女に笑いかけた。



もう大丈夫だよ……
あなたへの脅威は去ったわ……


魔力が限界を迎えたのか、それとも刺された影響か、すでに声が出ないので、私はありったけの気持ちを込めてあの子に笑いかける。
それから少しして、ようやくあの子は状況を理解したのだろう、ゆっくりと床に倒れる私に手を伸ばした。



あなたが……私を守ってくれたの……?


もうあまり動かなくなってしまった体の力を総動員して、ゆっくりと頷く。
すると、あの子はぽろぽろと涙を流しながら、ぎゅっと私を抱きしめた。



ごめんね……私を守ってくれてありがとう…………!


ぽたぽたと、あの子の涙が私に触れる中、ゆっくりと手を伸ばしてその涙を拭う。



もう一度あなたに会えてよかった……
あなたを守ることができてよかった……


そんな思いを込めながら、そっとあの子の涙を拭った私は、徐々に自分の意識が希薄になっていくのを感じる。
もうすぐ、私は完全に意識をなくしてただの人形に戻るだろう。
そうなる前に、と最後の力を振り絞って、何度も「ごめんね」と謝るあの子に囁きかけた。



……しあわ……せに…………なって……ね……


あの子は、一瞬目を見開いた後、大きく頷き、それを最後に私の意識は消え去った。
数ヵ月後。
とある街の結婚式場で一人の女性が愛する男性と結婚式を挙げた。
来訪者の話では、その女性の傍らには、色あせてボロボロになった一体の人形が綺麗に着飾った状態でおいてあったという。
