吸血鬼を信じるかと聞かれたことはあるだろうか?
俺はない。
厳密にはなかったという方が正しいかもしれない。
吸血鬼を信じるかと聞かれたことはあるだろうか?
俺はない。
厳密にはなかったという方が正しいかもしれない。
もちろん今までそんなことを聞かれた試しがないのだから、答えなど用意しているはずがない。
だが、相手が質問しているのだ。答えないわけにはいかない。
俺は困りながらも答えた
いるわけないだろう。
だが、現実は非情だ。
無いと思っていたものがある日突然現れる。
平気な顔をして。



――――


月明りに照らされた彼女は不気味に笑っていた。
喰われる。
口角を上げた時に見える八重歯からただならぬ気配を感じた。
感じた瞬間にはもう足が勝手に動いていた。



―――――――――


後ろを振り返ると鬼の形相をした吸血鬼が追ってきていた。
どのくらい走ったかもわからないが、家についた俺は急いで家に入り鍵を閉めた。
真っ暗な室内に一人へたり込む。
彼女の鬼の形相を思いだすだけで悪寒が走る。
とにかく部屋の明かりをつけようと立ち上がると、部屋に違和感を覚えた。
よく見ると窓が汚れている。
誰がこんないたずらしたんだよと思いながら窓に歩み寄った。
そこで目にしたのは
窓についた大量の血痕だった。俺は思わず腰を抜かした。
そっと窓に手を触れる。

血痕はなぜか外ではなく内側についていた。
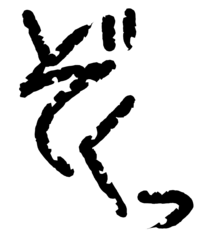
嫌な予感がする。
そっと振り返る。

笑顔でたたずむ吸血鬼を見て俺は後ずさりしかできなかった。
彼女は壁際まで追い詰め首元に噛み付いた。
身体の中すべての血液がすさまじい速さで抜き取られていくようだった
ドロリと生暖かい感覚が首筋を伝い胸元へと流れる。



――――


わずかに微笑んだ吸血鬼は窓を開け月に向かって飛び出していった。
