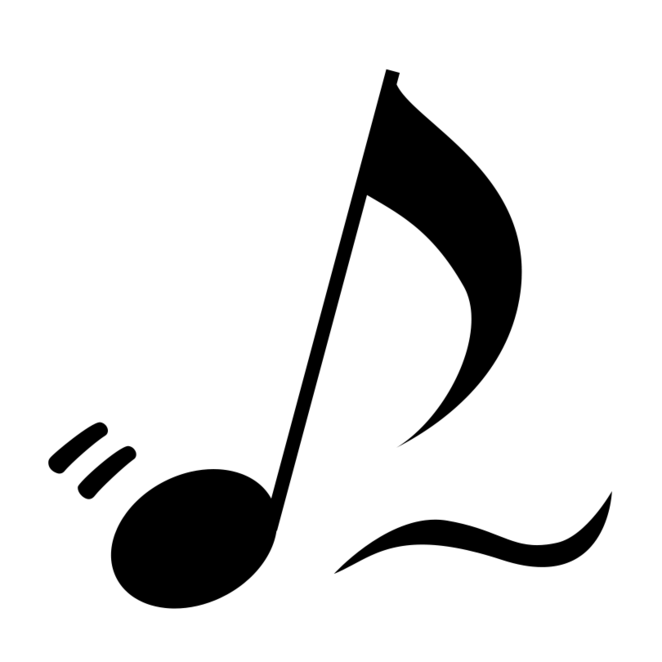あれ? 今私の名前が呼ばれたような。でも気のせいかな。だっていつも補欠だもん。誰かが体調や喉を悪くした時のために練習はするけど、本番に出たことはない。
あれ? 今私の名前が呼ばれたような。でも気のせいかな。だっていつも補欠だもん。誰かが体調や喉を悪くした時のために練習はするけど、本番に出たことはない。
メンバー発表が終わって、今日の部活はおしまい。メンバー表のコピーが部員の手に回されて、受け取った人から帰り支度を始めていく。
その中に、確かに私の名前があった。
私はまだ信じられなくて、呆然とメンバー表に視線を落としている。



おめでと、天ちゃん!


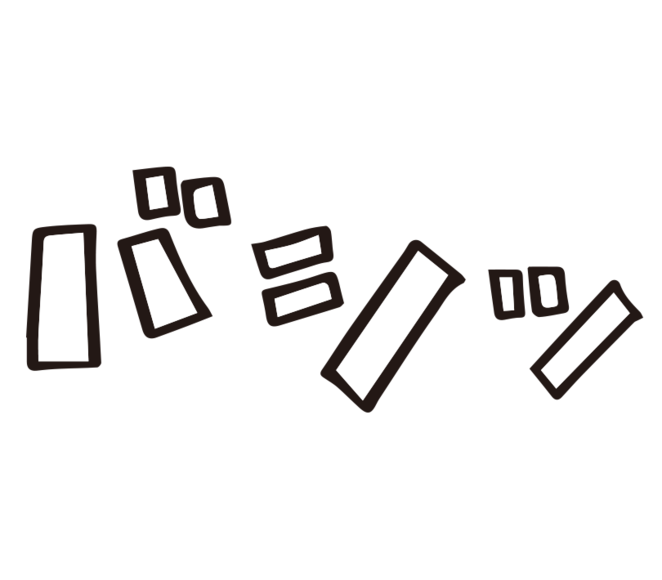
カバンを男らしく肩にかけた五十嵐先輩に背中を叩かれた。呆然としていたところの不意打ちだったから思わず前のめりに倒れ掛かってしまった。



諒! またそんなことしてっ!


後ろから日向部長の怒った声がして、五十嵐先輩は私の耳元でゴメン、と呟いた。



あ、大丈夫です。ちょっとびっくりしただけで





うん、じゃあ明日からも練習頑張ろうね


後ろから早足で追いかけてくる日向部長から逃げるように五十嵐先輩は部室を逃げ出す。追いかけていく日向部長を見送って私はようやく立ち上がった。



天ちゃん、帰ろっか





あ、うん


待ってくれていた小晴が後ろから私に声をかけた。メンバーに選ばれることも小晴にとっては当然のことで、別に特別なことじゃないはずなのに小晴は私が見たこともないくらい嬉しそうに笑っている。部員の姿はもうほとんどなくて、鍵を閉めて早く職員室に戻りたいらしい顧問の先生が入り口に立って私達を急かしている。
いつもはフラフラしていて私が手を引いてあげなきゃいけないところだけど、今日の小晴は機嫌よく歩を進めていく。私と同じ速度で歩いて顧問の先生に頭を下げて部室を後にした。



ビックリした?


まだ心の整理がつかない帰り道。小晴は下から私を覗き込むようにしながら微笑む。



え、何のこと?





秘密にしてたこと。五十嵐先輩に二人で朝練してて天ちゃんの歌声のこと聞かれたんだ





あ、そうなんだ


私も好きです、小晴はそう言っていた。好き、って言葉は別に人以外にも使う言葉だよね、確かに。皆揃っての練習だと一人ひとりの声をしっかり聞くことなんてなかなかないけど、小晴は別。毎朝私たちは二人で練習して二人きりで互いの歌声を聞いている。



何で言ってくれなかったの?


わかっているけど、聞いてみたかった。ビックリさせたかったっていうのはわかるけど、私があんなに悩んでいたのに小晴は何もおもってくれなかったのか、なんて欲張りなことを思ってしまう。



だって嬉しかったんだもん





え?


返ってきた答えは全然予想していないものだった。



天ちゃんが誤解してるのすぐにわかったよ。私だって同じくらい天ちゃんのことわかってるから。だから嬉しかった。天ちゃんが私に恋人ができるんじゃないかって焦ってるの





どういうことよ?


からかっていただけのようにも聞こえる小晴の言葉に本当に喜びの音が混じっていて、私はどんどん意味がわからなくなる。



天ちゃんは私と一緒にいてくれるんだな、って思って





そんなの、当たり前じゃない





当たり前なんかじゃないよ


小晴のソプラノボイスが私の耳元で囁かれた。
包み込むような歌声じゃなく、私の心だけを掴もうとするような力強い真っ直ぐな声。
思わず振り返ろうとした私を遮るように柔らかいものが私の頬に触れた。



え?





いつも言ってたよ、私。天ちゃんのことが好きだって


小晴の声はいつものほわほわした調子に戻っている。あの一瞬だけ中身がまるっと入れ替わったんじゃないかと思ったほど。でもその時の小晴を見ていない私には何もわからなかった。



天ちゃんは私のこと、どう思ってる?


今触れたのは小晴の唇だったんだ。そう気付いた瞬間に体中の熱がさっき触れられた右の頬に集まっていく。




私は


小晴を見るために視線を動かす。きっと真っ赤になっている顔を隠す気にもならなかった。私の顔を不安そうに見つめる小晴の顔も同じように真っ赤だったから。



私も、小晴のことが好き。友達じゃなくて、きっともう少し先の存在として





じゃあ、証明してみせて


立ち止まって小晴は私を見つめたままゆっくりとその大きな瞳を閉じる。少しだけ屈み込んで小晴と視線の高さを合わせた。
白い首筋に手を触れる。薄い唇に自分の顔が近付いていく。




なんで、ほっぺなの?





小晴だってほっぺだったじゃないっ! これでおあいこでしょ?





私は先にやったもん。天ちゃんズルい


小晴が両手で私の腕をぽかぽかと叩く。でも少しも痛くはなかった。
一瞬だけ触れた小晴の頬は、ホットミルクみたいに白く、温かく、ちょっぴり甘かった。



ほら、ちゃんとお返ししたわよ。帰ろっ


まだちょっと不満そうに頬を膨らませた小晴を急かす。
私達の顔は夕日で赤に染まった町並みの中でも一際赤くなっているに違いない。早足で歩き出した私を小晴が小走りに追いかけてくる。さっきと同じように右隣に追いついて、私の空いた右手を掴んだ。



つかまえた





つかまえられた


私もそっと手を握り返す。もう離すつもりはない、お互いに。



そうだ、結局小晴っていつも朝何時に来てるの? 私早くても頑張って起きるよ





いつも七時くらいかなぁ





早っ!


昨日の私が七時半だから、相当早く来ているつもりでそんなに小晴を待たせていたなんて。それならずっと朝練一番乗りができなかった理由もよくわかる。



なんでそんなことしてたのよ?





だって私が先に部室にいたら天ちゃん次の日はもっと早く来るでしょ? そうしたらどんどん長く一緒にいられるじゃない


そんなことしなくても約束すれば同じ時間に行ったのに。私だって小晴と二人きりで練習するのが好きなんだから。



待ってる間に勉強してたら成績も良くなったし、天ちゃん効果抜群だね





なんか納得いかないわ


私は成績イマイチなのに、小晴は私を待っているおかげで成績がいいなんて。



じゃあ明日は部室で朝勉強だね


えへへ、と笑った小晴に釣られるように私も笑った。
二人きりの帰り道、どちらともなく零れだした課題曲のデュエットが顔を出し始めた月に照らさせて街中に広がっていくようだった。